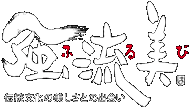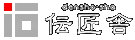母屋は残しても、蔵は解体してしまうという例が少なくありません。蔵には農具や冠婚葬祭の時に使う食器類、お雛様や五月人形など季節の品、収穫した一年分のお米や味噌などが納められていたものですが、今の暮らしにはそうしたものを取っておく必要が少なくなり、納める物とともに蔵自体も消えつつあります。
分厚い壁に見合った、重厚感のある、厚みのある大きな扉です。家の風格や豊かさを象徴するものなので、意匠的にも凝っているものが多いものです。「花かげ写真館」では、二つの使い方を提案しています。
ひとつは、広めの廊下のつきあたりを書斎にし、仕切りがわりに蔵戸を使った例。完全に閉鎖された空間ではないけれど、集中できる、そんなスペースを作る助けとなっています。引き戸ではなく開き戸にして、動かしやすいように下にキャスターを付けました。ついたてのように、空間のゆるやかな仕切りでありながら、蔵戸の重厚さから、中に居る人はちょっとした「お籠もり」気分になれます。
もうひとつは、寝かせた蔵戸に足をつけ、強化ガラスを上に置いてテーブルにした例。蔵戸の大きさが、居間のテーブルに案外ちょうどいいんです。凝った意匠も、真近で楽しめます。部屋の中心に際立ったアクセントになりますよ。

花かげ写真館奥の事務スペースの仕切り扉。蔵戸らしく、頑丈な鍵もつけました。

棟梁の家の1階に置かれた蔵戸テーブル。ガラスは蔵戸に密着させず、シリコンのスペーサーを入れて少し浮かせてあります。その隙間に昔の写真や古い物差しなど、懐かしさを感じるものを入れておきました。初めてのお客様でも会話がはずみます。