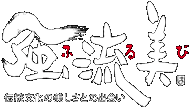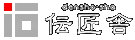県庁別館
甲府城の西側、平和通りの東側にある山梨県庁には、甲府の大空襲で焼け残った、昭和初期のままの建物があります。雨漏りなどでかなり老朽化していましたが、このたび、耐震工事も兼ねて、戦後に増築された4階を撤去、残された図面や写真をもとに昭和5年に創建された当時の姿が復元されました。当社は協力会社として参加、木工事と木製建具に携わらせていただきました。

1階 階段ホール
この建物の3階にあるこの旧正庁は、最も格式の高い部屋として重要な式典や公賓の接遇などに利用された部屋です。天井の高い部屋です。欅の木の舞台があり、椅子が並んでいます。知事が皆を集めて話をしたのでしょうか。

旧正庁
日本が洋風建築を取り入れはじめた明治の頃には、アーチ式の建物が多かったのですが、昭和初期ともなると、世界的にはより抽象的で直線的なオフィスビルが建つような時代。この建物も鉄筋コンクリートの四角い構成をしています。照明などには、フランク・ロイド・ライトが帝国ホテルで見せてくれたおしゃれな内装の影響も感じられませんか。

折上げ式格天井にそっくりの意匠
鉄筋コンクリート造でありながら、まっ白い漆喰の壁や天井に、木が随所に使われていて、無機質で近代的というよりは、どこか落ち着いた和の雰囲気が感じられます。
おもしろいことに、木部の仕上げ方に社寺建築に共通する技術が使われています。格子状の天井は、お寺の「折上げ式格天井」とそっくりですし、舞台のプロセニアムの上にも、肘木状の持送りような意匠も見えます。床は手の込んだ「矢羽根張り」。いずれも、大工が手間をかけた仕事です。

矢羽根張りの床
正庁ともなれば、社寺建築の心得のあるような、腕のいい大工が集められたはず。良質な木の手仕事によるディテールが、全体をやわらかく、格調高くまとめています。もちろん設計者が居たはずですが、この部屋の格式を演出するのに、日本の職人技術のボキャブラリーを自然と使っていたのですね。

扉には、社寺建築の意匠が
矢羽根張りの床は朽ちかけていたのですが、使えるパーツは大ばらしして一旦保管した後のち組み直し、使えない部分は、パズルをはめるようにして新しく造ったパーツに入れ替えました。気の遠くなるような作業ですが、職人たちががんばって、元の姿を再現しました。新しく作り替える方がうんと簡単なのですが、やはり、手間をかけてでも、古いものをなるべく残そうという方針で、そのようにさせていただきました。
甲府駅南口からすぐ。二階には山梨近代人物館も開館しました。いつでも自由に見ることができます。甲府駅近くに用事がある時には、ぜひお立寄りください。

ケヤキ材で復元した演壇。美しくアールを描くように仕上げました。
山梨県県庁別館 旧正庁
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
Tel:055-237-1111(代)
開館時間:午前9時〜午後5時
休館日:週1回又は月2回程度(土、日、祝日は原則オープン)観覧料:無料