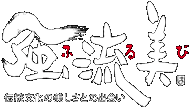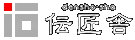日本家屋では、座敷などで畳の部屋の続き間が襖などで仕切られていることがよくあります。通常の部屋では襖の上部は、天袋や小壁となりますが、続き間の境にあたる場合は、隣の部屋との連続性をもたせるために、半開放的に仕切る「欄間」を用いることがあります。具体的には、障子、格子、透かし彫りや浮き彫りの彫刻などを施した板や木枠を、鴨居と天井との間にはめこみます。
欄間は、必要に応じて別の部屋としても使える続き間同士を、上部でひとつながりの空間にすることによって、採光や換気面での流れを生み出すはたらきを果たしています。欄間に施される意匠は、その家の主の趣味趣向や家の格を体現するものでもあります。
欄間彫刻の本場として有名なのが、富山県砺波市井波です。彫刻師が欄間を制作する店が軒を並べ、その仕事ぶりや作品が表通りを散歩しながら見ることができるのは、なかなか面白いものです。具体的で装飾的な表現に強い彫刻欄間と対局にあるのが筬欄間(おさらんま)。建具職人が組子や千本格子など、細い材で、精巧で緻密な幾何学模様を作ります。
「風流美」の観点からすると、筬欄間は、現代の暮らしに取り入れることのできる可能性の高い素材です。職人の手仕事が生んだすぐれた意匠を、ポイントで効果的に活用したいものです。

筬欄間